ときわようちえんの願い

心を豊かに育てる

「うちゅうくらい うれしい!」
幼稚園は子どもが最初に出会う小さな社会。そこでもあるがままの自分が受け入れられ、愛される体験。それはゆるぎない根っこの自己肯定感となってその子の人生を支えます。
みんな自分が好きになる。みんなお互いを認め合う。
ときわようちえんは、聖書の語る神の愛に根ざし、豊かな心を育てます。
家庭的で自然な交わり

「てつだったろか?」 「やってみる!」
ときわようちえんは、より豊かな子どもの育ちのために「異年齢・家庭的保育」を行っています。核家族化や少子化が叫ばれる現代。年齢の異なる子どもたちがひとつの家族のように一緒に生活する体験はとても貴重なものだと思います。
保育者はたえずひとりひとりに目を注ぎ、その子の歩調に合わせて見守ります。自分の居場所を見つけた子どもたちは、安心して自分らしさを出せるようになります。そして友だちとの違いを認め合い、共に生きる喜びを味わえるようになります。


じっくり、たっぷり、
本気で遊びこむ

「せんせい のぼるから
みとってな!」
よく目にする「遊びが大切」という言葉。確かにその通りですが、大切なのは遊びの「質」です。ただ遊ぶのではなく、「遊び込む」こと。その子自身の興味関心をとことん突き詰めていく。湧き出る発想を創意工夫して形にしていく。感性の赴くままに体を、心を、絵筆を動かしていく。異なる個性と交わり、時にぶつかりながら、自分と他者を発見していく。
本気の遊びを通して、子どもたちは日々たくさんのことを学び取っていきます。そのために欠かせないのは、ゆったりした時間と安心できる空間。
ときわようちえんには今日も、じっくり、たっぷり遊びこむ、子どもにたちとって理想的な時間と空間がひろがっています。

家庭的・異年齢保育
幼稚園が「ひとつの家族」
~家庭的・異年齢保育~
「子どもの育ちにとって
一番理想的なのは
どのような環境だろう?」
常盤幼稚園では一つの答えとして、
幼児教育先進国である北欧などでスタンダードになっている
「異年齢(縦割り)保育」を実践しています。

互いに育ち合う異年齢保育

日常的に異年齢の子どもが一緒に生活することで、子どもたちには様々な力が芽生えていきます。互いを思いやる力や、人間関係を築き、維持する力、コミュニケーションの力、多様な考えを受け入れ、様々な角度から物事を観察する力…知識の詰め込みだけでは決して得られない「生きるための力」が、自然に育まれます。
入園した時は末っ子。年上の子どもたちに優しくされ、憧れながら。一つ大きくなったら、今度は自分が、してあげる。いつも身近に、ちょっと先のボク、少し前のワタシがいる。子どもたちが互いに育ち合うこのような環境は、子どもたちの心をより豊かに育み、人としての「根っこ」を大きく深くしていきます。
※2歳児につきましては、生活リズムの関係で一つのクラスを設けています。自由遊びの時間は上の子たちと一緒に過ごします。
一人一人に目の届く保育環境だからこそ

年齢や発達段階の異なる子どもたちが日常的に一緒に過ごす本来の異年齢保育は、保育者の目がひとりひとりに届く少人数の家庭的な園だからこそ可能な取り組みです。
子どもたちの安全や環境構成には十分に配慮しております。


発達に応じた活動も充実しています!

異年齢の交わりと並んで、発達段階に応じた活動も充実しています。一つ大きくなるごとにできるようになる活動が増えていきます。5歳児だけしかできない活動もたくさんあります。小さい子たちは羨望のまなざしで。大きな子たちは誇らしげに。ほんとうの「きょうだい」のような交わりです。
クラスでの過ごし方
みんな同じクラスだけど、
年齢に応じてできることがたくさん増えます!!
年齢に応じた活動表
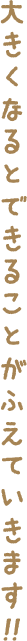
きいちご組
(2歳児)
- はだしで遊ぶ
- どろんこ遊び
- えのぐで描く
- フィンガーペインティング
- 園外保育(外宮さんまで)
年少組
(3歳児)
- クッキー作り(クリスマス)
- 朝熊山登山(7町まで)
- 園外保育
…おたまじゃくしとり
…どんぐりひろい
…おいもほり
…お別れ遠足 - マザーグースお話の会
- 木工
- フラワーアレンジメント
年中組
(4歳児)
- 絵本の貸し出し(1冊)
- 食事作り
- 朝熊山登山(22町まで)
- 針と糸で縫う
年長組
(5歳児)
- 絵本の貸し出し(2冊)
- パラバルーン
- トランポリン
- お泊り保育
- 陶芸
- ハンドベル
- 小学校たんけん
- 名古屋市科学館見学(プラネタリウム)
各クラスの募集要項に関しては
こちらをご覧ください。
園長から、お父さんお母さんへ
めいっぱい、「今」を生きよう。
ランドセルのチラシがどんどん早く届くようになっています。子どもたちはどんどん先へと急かされています。でも、子どもが「子ども」でいられる一生に一度のスペシャルな数年間を、「先を急ぐ」ことに使ってしまってよいのでしょうか。
見せてあげたいものがたくさんあります。小さな手で触れてほしいものが山ほどあります。今しかできないことが目の前にあふれているのです。だからせめて幼稚園時代は、めいっぱい「今」を生きてほしい。何も心配しないで、誰とも比べられないで、あるがままの自分で生きる喜びをお腹一杯味わってほしい。子ども自身が明日を築くチカラは、めいっぱい「今」を生きることによって育まれていくものです。なのに先々を心配するあまりオトナが子どもの大切な「今」を取り上げてしまってはいないでしょうか。子どもたちのこの先の長い人生を思えばこそ、子どもが「子ども」でいられる人生最初のかけがえない数年間をしっかりと守ってあげたい。私たちはそう願っています。
心配事もあるでしょう。でも、だいじょうぶです。こたえは子どもの数だけあります。この子の「こたえ」は、この子の中にちゃんとあります。それを探すために、私たちは子どもたちと共に毎日を探検したいのです。だいじょうぶ。子どもは幼稚園で、笑ったり泣いたり、走ったり転んだりしながら、私たちの想像など軽々と越えて成長していきます。
さあじぶんを、探検しよう。
園長 山口元気


園長 山口元気

ときわようちえんの生みの親

「この町の子どもたちに神の愛を―。」
米国からの婦人宣教師ジェッシー・ライカーのあつい祈りによって常盤幼稚園は生み出されました。1913年(大正2年)に開園以来、一貫して神の愛、キリスト教の教えに根ざした保育を行っています。「神さまからいのちを与えられたひとりひとりが、神さまに愛されている子どもとして成長していくように―。」昔も今も変わらない常盤幼稚園の祈りです。
常盤幼稚園は戦後、日本キリスト教団山田教会の幼稚園として歩み、1998年より学校法人として再スタート。ライカー女史の後は歴代の山田教会牧師が園長を務め、園生活の中で子どもたちに神さまの愛を伝えることを大切にしています。


「庭で綱引き」1915年(大正4年)頃
